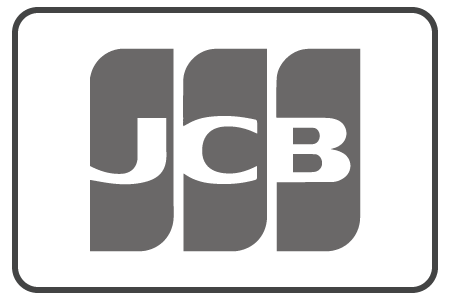自転車を運ぼう!
Staff Note | 2020.08.03

こんにちは、Tokyobike Shop 中目黒の西村です。
今回は、以前京都から東京まで新幹線に乗って自転車を運んだ時のことをご紹介します!
旅先で、「自転車があればもっと楽しいだろうな」「友達とサイクリングしたいな」と思うことはありませんか?
自転車は、きちんと専用の袋に収納すれば公共交通機関で運ぶことができます。
袋に入れる際は少々解体作業が必要で、ある程度の持ち運べる大きさにして収納します。
このようして自転車を運ぶことを「輪行」と言います。
見知らぬ地でも気の知れた相棒がいれば心強いですし、街探索がもっと楽しくなるはず。
とはいえ、「なんだか大変そうだ・・・」と勇気足りずになかなか輪行に踏み出せなかった私。
意を決して、初めての輪行に挑戦してみました!
ここではざっくりとした輪行の流れをご紹介します。
もし「これなら私でもできそうだ!」と感じられたら、ぜひ一度挑戦してみてくださいね。
まず、自転車にカゴや泥除けなどアクセサリーが付いている場合は取り外しておきましょう。
そして、変速機がある車体の場合は下準備にチェーンを内側へ移動させます。
一番軽いギア設定にしていただければ大丈夫です。

今回詰める輪行袋は前輪のみを取り外すタイプです。
写真左のブレーキ部分(ブレーキキャリパー)を解放し、車輪中央にあるレバー(写真右)を引いて車輪を取り外します。
tokyobikeではTOKYOBIKE SS、MONO、LITE以外の大人車には、クイックリリースと呼ばれるこのレバーが付いているので工具無しで車輪の着脱が可能です。



車輪を外すと、もともと車輪が挟まっていた部分のフレームが二股に分かれているのがわかります。
この「フォーク」という部分は、車輪を取ってしまうと衝撃で曲がってしまう恐れがあるため、間をしっかり固定をします。

この時、細長い「エンド」というパーツを間に挟んで固定します。
輪行を行うときは、輪行袋とこの「エンド」が最低限、自転車とは別途必要になります。
ここまで終えると、もう一息!
実際に袋に入れる時、中で車輪が動かないように車輪をフレームに固定させます。
ハンドルバーは変速機がある方に首を折り曲げておきます。

写真のように、ペダルを下にして車輪を置くと安定しやすいです。
そして、輪行袋にセットでついてくるストラップを使って車輪をフレームに縛ります。


固定をすると持ち上げても車輪が落ちなくなります。

この状態で袋に入れれば完成です!

エンドを使って固定したフォークの下部やペダルなど、鋭利な部分は緩衝材や専用カバーで守ってあげるのがオススメです。
ここでは前輪のみ外しましたが、後輪も外すことができればさらに小さく袋詰めできます。
いかがでしたでしょうか。
私は初めてやってみて、なんだか自転車と自分の可能性が広がった気がしました。
今回は細かい説明は省略しましたので、もしご興味あればtokyobike直営店やお近くの自転車屋さんで一度ご相談されてみてください。
一度一人でやってしまえば、結構自信がついてしまう作業です。
ちなみに2020年5月より、東海道新幹線では特大荷物(3辺の合計が160cmを超える荷物)のルールが変更になります。
特大荷物を持ち込む際は、事前に「特大荷物スペースつき座席」(最後部座席)を予約する必要があります。
詳しくはJR東海のウェブサイトでご確認ください。
その他公共交通機関に関しても、それぞれでルールが異なりますので事前にご確認の上、楽しく輪行に挑んでみてくださいね!
Tokyobike Shop 中目黒 staff:西村 夢見